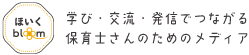保育士のメンタルに効くプチコラム「ぶるーむサプリ」です。
保育に役立つ心理学の新シーズン6回目は、「メラビアンの法則」です。
あなたの職場はいかがでしょうか?
——————————————————–
前回は「嫌われる勇気」のお話をしました。
少し前に、
「人は見た目が9割」という本もはやりましたね。
今日は「メラビアンの法則」のお話です。
メラビアンの法則について聞いたことはありますか?
メラビアンの法則とは
アメリカの心理学者アルバート・メラビアン(Albert Mehrabian、1939年 ~) が提唱した法則です。「感情や態度」が矛盾したメッセージとして伝えられたときに、メラビアンの法則では、コミュニケーションに影響を与える要素として、「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の3つを提示しています。それぞれが相手に影響を与える割合の一覧は、次のとおりです。
- 視覚情報(表情・態度・身振り)55%
- 聴覚情報(声のトーンや話し方)38%
- 言語情報(言葉そのもの)7%
もっとも大きな影響を与えるのが、表情やしぐさといった視覚情報だといわれています。声のトーンや大きさなどの聴覚情報が最も影響を与える要素、話の内容を表す言語情報はわずか7%となっていますが、これはあくまでも非言語コミュニケーション(言葉以外の情報)の占める合計が93 %に及ぶのは、言っている言葉(言語)と、とっている口調や表情(視覚、聴覚)に矛盾が発生する場合のことであるとされています。
例えばこんなシチュエーションのときを想像してみてください。
新人保育士A子さん。まだ保護者対応に慣れていません。ある日、B君のママから連絡帳で「A子先生がいつも、お迎えのときにその日の様子を伝えてくれなくて、とてもモヤモヤしています」と書いてきました。
クラスリーダー:B君のママがこんな風に言ってるね。気にしなくていいよ。保護者対応は私がしばらく変わるね。(口調はやさしいが、目線を合わせない。怒り呆れているような表情)
A子さん:は、はい……申し訳ありません(萎縮してしまう)
いかがでしょうか。もしあなたがA子さんなら、どんな感情を持つでしょうか。
「気にしなくていいよ」と口では言っているけれど、表情から「怒ってるのかな」「呆れちゃったのかな」という印象を受けたことが、言葉より視覚的な情報として先に入ってきて、それに囚われてしまうのではないでしょうか。
相手の気持ちを考えた言動を心がけてはいても、あなた自身もクラスリーダーと同じような対応をしていることがあるかもしれません。
緊張する場面でこそ、にこやかな表情や眼を見てはきはきとした話し方を心がけると、相手に好印象をもってもらいやすくなります。
また、身だしなみも重要な非言語コミュニケーションの一つです。
メラビアンの法則を実践する第一歩として、まずは保育士に相応しい身だしなみになっているかチェックするところからはじめてみましょう。
メラビアンの法則は、保育士の仕事において非常に役立ちます。特に子どもや保護者とのコミュニケーションにおいて、その本質が活かされます。
【保育士の仕事への応用】
① 子どもとの信頼関係の構築
小さな子どもは言葉の意味をすべて理解できないことが多く、保育士の表情や声の調子、動作など非言語的な情報に大きく影響されます。優しく穏やかな声や笑顔で話しかけることが、安心感や信頼感を生みます。ただし、昨今では、声が大きすぎたり、言葉数が多すぎる保育士もいますので、まずは自分が保育の中で、子どもたちにどんな印象を与えているか、振り返ってみるのはいいですね。
② 保護者対応での信頼形成
保護者との連絡や相談時にも、言葉以外の態度や表情が大きく影響します。例えば「大丈夫ですよ」と言っても、声が不安そうだったり表情が曇ったりしてたら、相手は不安になります。一貫した安心感のある対応が求められます。
③ 職員同士のコミュニケーション
保育現場はチームワークが重要です。「ありがとう」や「お願いします」といった言葉にふさわしい「目線」「態度」「声のトーン」が伴うことで、信頼関係が強まり、職場の雰囲気も良くなります。
【まとめ】
メラビアンの法則を意識することで、「どう伝えるか」を大切にでき、言葉以上の信頼や安心感を子どもや、保護者、同僚に与えることができます。保育士の「表情・声・態度」は、子どもにとっての“安心の土台”とも言えるでしょう。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)