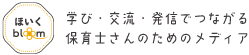今回も保育の現場でよくみられる?事例から
「認知バイアス」について考えたいと思います。
——————————————————–
認可保育園勤務の保育士Aさんは、
1歳児クラスの担任です。
複数の先生とチーム保育で頑張っています。
でも、やっぱり、「合わないメンバー」がいて……
保育の場面で、Aさんが取った行動に対し、合わない同僚Bさんが
「そのやり方だと、効率的じゃないと思います。みんなに合わせてもらえませんか」
と言ってきました。
とてもイライラしているようすです。
朝の受け入れで、保護者にあいさつし、子どもの荷物をロッカーにしまう、
というルーティーンの場面です。
Aさんは、その圧をかけるようなBさんの言い方に
一日中モヤモヤしてしまい、
次の日には、「保育園に行きたくないな」という気持ちにもなりました。
Aさんも「どうしたら受け入れがスムーズになるか」を
一生懸命考えて動いていたのに、頭ごなしに否定された気分です。
そして「このやり方をしたら、また怒られるんじゃないか」と
ビクビクするようになってしまいました。
数日後、そんな元気のないAさんの様子を見て、主任が声を掛けました。
「何かあったの?」
そこでAさんは思い切って主任に一連の出来事について打ち明けました。
これまでにも色々合わない部分があって、とても悩んでいることを話したのです。
主任は、うんうん、そうだね、とうなずきながらAさんの話を聞いてくれました。
「AさんはAさんなりに考えて動いているんだもの、あなたは正しいよ」
と言ってくれたのです。そして続けて言いました。
「でもね、Bさんも、『自分が正しい』と思っているんだよね。それぞれ、価値観や考え方は違うからどうしても、ぶつかってしまうもの。今度クラス会議で腹を割って話してみましょう。私も入るから」
「え、でも、私が言いつけたと思われてしまいます…」
「大丈夫。Aさんが言ったからではなく、私も事前に朝の受け入れに入って、体験してみるから」
こうして主任がうまく立ち回ってくれたおかげで、クラス会議では違和感なく、Aさんの意見も取り入れられ、
「このやり方はもっとこうしたら、スムーズかも」
「どうしてこのやり方をしているかというと、こうしたほうが早いと思うからです」
など、いつもは意見を言わない人も発言することができました。
Aさんは主任に感謝するとともに、くさくさして落ち込んでしまった気持ちを
前向きに変換することができました。
Bさんとも、以前よりは苦手意識を持つことなく会話ができるようになりました。
主任が話しかけてくれ、自分の気持ちを打ち明けたことが功を奏したと言えます。
ここで働いていたのは「自己中心的公正バイアス」です。
「あなたは正しいよ」と身近な人に肯定されることで安心することができたのです。
「社会的妥当性」とも言います。
「あなたは正しいけど、Bさんは間違っている」とは、決して言いませんでしたね。
Aさんの意見も認めて安心してもらったうえで
「みんなの意見も聞いてみよう」という
流れにもっていってくれた主任はさすがですね。
悩んだときには、まず「自己開示」をすることも大切です。
ひとりで悶々と悩んでいるなら、
身近な信頼できる人に、「こういうことがあったんですが、どう思いますか」と
相談してみましょう。その人の客観的な意見を取り入れることだけでも
突破口が開け、自己成長の階段をまたひとつ上がることができると思います。
———————————————————–
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)