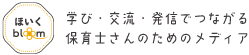保育士のメンタルに効くプチコラム「ぶるーむサプリ」です。
保育に役立つ心理学の新シーズン11回目は、「バーナム効果」です。
——————————————————–
テレビのバラエティ番組や情報番組、あるいは雑誌などで「今日の運勢」などのコーナーを見たことはありますか。
「あれ、今日は占いの結果が自分にぴったり当てはまっているな」と感じることがあるかもしれません。
そのような心理現象を「バーナム効果」と呼びます。
バーナム効果とは、誰にでも当てはまるような一般的な表現を「自分だけの特徴」だと捉えてしまう傾向のことを指します。例えば、「人に優しい一方で、傷つきやすいところがある」という結果を言われたとき、多くの人が「まさに自分だ」と感じてしまいます。
【バーナム効果とは】
- 誰にでも当てはまる曖昧で一般的な表現を「自分のこと」と感じやすい心理傾向
- 占いや性格診断でよく見られる現象
この効果は一見すると単なる錯覚ですが、保育士の働き方において役立つ側面があります。
例えば、自己理解や同僚理解のきっかけづくりに活用できます。園内研修で性格診断を取り入れると、バーナム効果によって「自分の強みや課題を知った気もちになる」ことで、前向きな行動につながる場合があります。
一方で、注意も必要です。バーナム効果に依存しすぎると、実際の自分の行動や状況を客観的に見られなくなったり、他者に対する思い込みを強めてしまう危険があります。たとえば「あなたは細かいことを気にするタイプですね」と言われて、それを思い込んでしまうと、本来の柔軟さや強みを見失うことにもつながりかねません。
【バーナム効果の効果と注意点】
- (効果)自己理解・同僚理解のきっかけになる
- (注意点)思い込みにとらわれすぎると、本来の姿を見失う可能性がある
保育の現場においては、子どもや保護者との関係でもバーナム効果が影響します。例えば、保護者が「うちの子は人見知りで…」と言ったとき、多くの子に当てはまるかもしれない特徴を「その子特有の特別な課題」と受け取りすぎてしまうことがあります。
また、子どもに対して「やさしいね」「おりこうさんだね」などと画一的な言葉をかけると、子ども自身がそのイメージに囚われてしまい、分の行動をその枠にはめ込んでしまい、「良い子でいなくては」と思い込んでしまうということもあるかもしれません。
保護者に対しても「よくあることですよ、大丈夫ですよ」と、子育て支援のつもりで言ったつもりが、「うちの子は違うのに……。担任は、子どものことを見てくれているのだろうか」などと、不満や不信感を持たせてしまう事例もあります。
そのため、保育士は「一般的な表現が持つ影響力」に自覚的であることが大切です。声かけをする際には、曖昧な言葉がけではなく、「今日は友だちにブロックを貸してくれてありがとう」「泣いていたお友だちにティッシュを渡してくれたね」「〇〇くんは、今日は一生懸命靴下を履こうとしていましたよ。少しずつですができることも増えていますね」といった具体的な事実を伝えることで、子どもはより健全な自己理解を育むことができ、保護者との信頼関係も深まります。
【保育現場での留意点】
- 保護者や子どもに対する思い込みに注意する
- 一般的な言葉よりも、具体的な行動をフィードバックする
- 子どもの自己理解を支えるために、曖昧なラベルづけを避ける
バーナム効果そのものは、人間に共通する自然な心理傾向です。否定するのではなく、適度に活用しつつも、その限界を理解しておくことが重要です。保育士がこの効果を理解していれば、自己理解や職員間の関係性づくりに役立てる一方で、子どもや保護者に対しては思い込みを避け、より客観的で根拠に基づいた関わりを選択できるようになります。
まとめ
- バーナム効果は「誰にでも当てはまることを自分に特有だと思う心理」
- 自己理解やチームビルディングのきっかけとして活用できる
- 一方で思い込みやラベルづけには注意が必要
- 子どもには具体的な事実を伝える声かけを心がけることが望ましい
バーナム効果を正しく理解することは、保育士が自分や周囲を冷静に見つめ直し、子どもや保護者に寄り添う視点をより豊かにするためのヒントとなります。心理の仕組みを知り、日々の実践に活かすことが、保育の質を高めることにつながるのです。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)