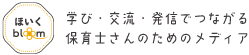保育に役立つ心理学の新シーズン9回目は、「モチベーション」です。
——————————————————–
保育士という仕事は、日々子どもたちの成長に寄り添い、未来を育む、やりがいのある仕事です。その一方で、体力的にも精神的にも大きなエネルギーが必要であり、ときにモチベーションの維持が難しく感じる場面もあるかもしれません。
忙しい日々の中で、「今日はなんだかやる気が出ない」「子どもたちの前では元気にふるまっているけれど、内心は疲れている」そんな思いを抱くのは、決して特別なことではありません。
このコラムでは、保育士としてのモチベーションをどう保ち、どう回復させていくか、そのヒントを具体的にご紹介します。
1.モチベーションとは何か?
まず、「モチベーション(motivation)」とは、自分を行動に向かわせる“心のエネルギー”のことです。モチベーションには大きく2つの種類があります。
- 外発的モチベーション:給料、評価、他者からの承認など、外から与えられる要因によって動機づけられるもの。
- 内発的モチベーション:自分のやりがいや楽しさ、好奇心、達成感など、内面から湧き上がる動機。
保育士という職業は、この「内発的モチベーション」がとても重要です。なぜなら、子どもたちはすぐに成果が見える対象ではなく、長い目で成長を見守る仕事だからです。
2.なぜモチベーションが下がるのか?
どんなに保育の仕事が好きでも、モチベーションは波のように上がったり下がったりするものです。特に以下のような要因が重なると、やる気を失いやすくなります。
- 人間関係のストレス:同僚や保護者とのコミュニケーションに気を遣い続けることによる疲労感。
- 達成感の不足:子どもの変化や成長が見えにくく、自分の努力が実っている実感が持てない。
- ルーティンワークによる飽き:毎日が似たような繰り返しに感じられ、やりがいが薄れてくる。
- 体力的な疲労や睡眠不足:疲れがたまると、心のエネルギーにも影響が出ます。
大切なのは、「モチベーションが下がること=悪いこと」ではないということです。誰にでも起こり得る自然な反応として受け止めましょう。そのうえで、回復の手段を持っているかどうかが鍵になります。
3.モチベーションを保つための5つの工夫
① 成長を「見える化」する
子どもたちの小さな成長や、自分の工夫した保育がうまくいった場面などを、ノートやメモ、写真で記録する習慣を持ちましょう。もちろん紙ではなく、スマホでもOK(ただし写真の取り扱いについては各職場のルールに従ってください)。自分だけの成長記録として、客観的に振り返ることで、「自分の仕事は意味がある」と再確認できます。
② 自分自身をねぎらう時間を作る
「今日はこんなことができた」「この子が笑ってくれた」など、1日の終わりに自分を褒める時間をつくりましょう。保育士はつい他人を優先しがちですが、自分への労いはモチベーションの土台になります。そして日々は同じことの繰り返しではありません。あなたも、そして子どもたちも、少しずつでも成長しています。それを楽しみながら観察していきましょう。
③ 他者とつながる
同じ立場の保育士同士で経験を共有することは、心の支えになります。職場の仲間と日々の出来事を話したり、外部の勉強会やSNSで全国の保育士とつながったりすることで、孤独感を減らし、刺激を得ることができます。そして保育士としての自信や誇りにつながっていくことでしょう。
④ 自分の「好き」を取り戻す
保育の中でも特に好きな活動――絵本、製作、リトミック、自然遊びなど――に改めて力を入れてみましょう。「好き」を原点に戻ることで、内発的なやる気が再び湧いてきます。「来月の活動で、こんなことをしてみたいな」と積極的に発信してみましょう。きっと同僚も後押ししてくれるはずです。
⑤ プロとしての目標を持つ
中長期的に「こうなりたい」というビジョンを持ちましょう。例えば「3歳児の保育が得意な保育士になりたい」「子どもへの言葉がけをもっと磨きたい」など、明確な目標があることで、日々の行動に意味が生まれます。
モチベーションは、一度下がったからといって終わりではありません。むしろ、日々の小さな選択や行動によって「育てていく」ものです。疲れを感じたときは、自分に問いかけてみてください。
- 「今日はどんなことで笑った?」
- 「誰かに感謝された瞬間はあった?」
- 「自分の力が役に立ったと思える場面は?」
その答えの中に、あなたのモチベーションを支えるヒントがきっとあるはずです。
子どもたちは、あなたの存在を感じ、言葉を聞き、関わりの中で成長しています。
小さな毎日の積み重ねが、楽しく明るい未来を、いま、まさに育てています。自分の心のエネルギーを大切にしながら、これからも保育士として輝き続けてくださいね。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)