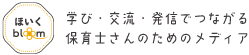保育士のメンタルに効くプチコラム「ぶるーむサプリ」。
保育に役立つ心理学の新シーズン11回目は、「コーピング」です。
——————————————————–
保育士は、子どもの成長を支えるやりがいの大きな仕事である一方で、心理的にも肉体的にも、日々の業務の中に多くのストレス要因が潜んでいます。
例えば、保護者との関わり、職員間の人間関係、行事や書類業務の負担、そして子どもの安全を守る責任など…緊張感と責任感を持って働いているという意味では他の職業も同じですが、何よりも、乳幼児の生命をお預かりするプロフェッショナルである以上、ストレスの大きさや内容は特殊であるといえます。
【ストレスの主な要因】
- 保護者対応や職員間の人間関係
- 行事や書類業務による時間的プレッシャー
- 子どもの安全を守る責任の重さ
上記のような要因は、保育士の心身に少なからず影響を与えます。
このようなストレスと上手につきあうために、有効とされるのが「コーピング」です。コーピングとは、ストレスを感じたときにその影響を和らげたり、乗り越えたりする工夫や行動のことを指します。
コーピングの方法には下記の2種類あります
【コーピングの種類】
- 問題焦点型コーピング:ストレスの原因を直接解決する方法
- 情動焦点型コーピング:気持ちを落ち着けたり、気分転換を行う方法
この二つの方法を、場面に応じて使い分けることがストレス対処法として効果的だといわれています。
例えば、行事準備の負担が大きく、特定の人に負荷がかかってしまっている状況があったとします。その場合には業務の分担や進行管理を見直す「問題焦点型コーピング」が有効です。
一方で、繁忙期に避けられない疲労を感じたときには、趣味や休息、軽い運動などで気分を切り替える「情動焦点型コーピング」が役立ちます。
【具体的な実践例】
- 行事準備の負担 → 業務分担や進行管理の見直し(問題焦点型)
- 繁忙期の疲労感 → 趣味やリラックス法で気分転換(情動焦点型)
個人だけでなく、職場全体で取り組むことも重要です。保育はチームで行う仕事であるにもかかわらず、誰にも相談できずに、「私ががんばらなくては」と、一人で抱え込んでしまい、限界を感じてしまう場面も少なくありません。
そういった状況を防ぐためにも、職場全体での取り組みを、普段から業務の一環として取り入れるようにすると良いでしょう。
【職場全体での取り組み】
- 定期的なミーティングで課題や不安を共有する
- 職員の得意分野を活かして仕事を分担する
- 「ありがとう」など感謝の言葉で互いを支える
加えて、保育士自身がセルフケアの習慣を持つことも欠かせません。仕事と生活のバランスを意識し、休息や趣味の時間を大切にすることは、翌日の活力につながります。
【セルフケアの工夫】
- 仕事と生活のバランスを意識する
- 趣味や休息の時間を意識的に確保する
- 日常の小さな習慣(お茶を飲む、子どもの笑顔を思い返す)を活用する
園としても、ストレスマネジメントやコーピングを学ぶ研修を行ったり、リーダーが率先して実践する姿勢を示したりすることで、相談しやすい職場づくりにつながります。
【園としての支援】
- ストレスマネジメント研修の実施
- 管理職・リーダーが率先してコーピングを実践
- 安心して相談できる風土を醸成
保育士は子どもにとって「安心できる大人」であることが求められます。そのためには、まず自分自身が安心できる環境で働き、心身を整えておくことが必要です。コーピングは特別な道具や長い時間を必要とするものばかりではなく、日常の小さな工夫から始められます。
【コーピングの効果まとめ】
- ストレスをゼロにはできないが、適切に対処することでやりがいを保てる
- コーピングの実践は、子どもへの関わりや園全体の雰囲気改善につながる
ストレスをうまく乗り越える力を身につけることは、保育士が健やかに働き続けるための大切な基盤です。小さな工夫を積み重ねながら、自分に合ったコーピングを見つけていくことが、より良い保育の実現につながっていきます。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)