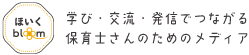保育士のメンタルに効くプチコラム「ぶるーむサプリ」です。
保育に役立つ心理学の新シーズン12回目は、「燃え尽き症候群」です。
——————————————————–
保育士の仕事は、気づかないうちにストレスを溜めがちな仕事でもあります。
日々子どもたちの成長を支え、同僚と協力しながらクラスを運営し、行事の準備や保護者対応……毎日が矢のように過ぎていきます。「自分は大丈夫」「まだまだやれる!」「気合いだ!」などと思っていても、気づいたときにはメンタルがヘトヘト……中でも注意したいのが「燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)」です。
燃え尽き症候群とは?
燃え尽き症候群とは、強いストレスや過度の責任感のもとで頑張り続けた結果、心身のエネルギーが枯渇してしまう状態をいいます。
代表的な症状は以下の3つに整理されます。
- 情緒的消耗感:心が疲れ切り、常にだるさや無気力を感じる。
- 脱人格化:子どもや保護者、同僚への関心が薄れ、冷淡な態度や投げやりな気持ちが出てくる。
- 達成感の低下:自分の仕事に意味を見いだせず、「頑張っても無駄」と感じてしまう。
これらが重なると、保育への情熱ややりがいを失い、日常生活にも影響が及ぶことがあります。
特に医療職、教育職、介護職など「人と深く関わる仕事」に多く見られるそうです。しかしもちろん、一般的な会社員や学生など年齢を問わず起こり得る心理的な症状です。
保育士を取り巻く、燃え尽きの要因には次のようなことが考えられます。
- 感情労働の大きさ:子どもへの愛情を注ぐ一方で、イライラや疲労を表に出せない。
- 保護者対応の難しさ:要望や相談に応える中で、自分の感情を抑え込みやすい。
- 多忙な業務量:書類作成、行事準備、研修などが重なり、慢性的な時間不足になる。
- 理想と現実のギャップ:「子ども一人ひとりに寄り添いたい」という思いと、実際の人員配置や制度上の制限との間に矛盾が生じる。
- 自己犠牲の傾向:真面目で責任感の強い保育士ほど、自分の健康やプライベートを後回しにしがち。
燃え尽きのサインに気づく
次のような症状が続いていませんか? 一つでも当てはまれば、もしかしたら燃え尽きのサインかもしれません。
- 朝起きても疲れが取れない
- 仕事に行くのが憂うつで仕方がない
- 子どもの声や泣き声に過敏に反応してしまう
- 保護者対応がつらく、避けたい気持ちになる
- 「自分なんて役に立っていない」と感じることが増えた
- 趣味や食事、友人との会話など、以前楽しめたことに興味が持てない
こうした兆候を「自分の弱さ」と責めてしまう必要はありません。むしろ、頑張ってきた証拠であり、早めに立ち止まるサインと考えることが大切です。
どう向き合えばいい?
燃え尽きを防ぐには、日常の中で少しずつ「自分を守る工夫」を取り入れることが効果的です。
1. 感情を言葉にする
イライラや不安をため込むと疲れが増します。信頼できる同僚や友人に「今日は本当に大変だった」と素直に話すだけでも、心が軽くなります。
2. 休む勇気を持つ
「子どもや同僚に迷惑をかけたくない」と無理をしがちですが、休養は長く仕事を続けるために不可欠。休むことは責任放棄ではなく、自分と子どもを守る行為です。
3. 小さな達成を意識する
「今日は〇〇ちゃんが笑顔を見せてくれた」「一つ書類が終わった」など、小さな成功に目を向けることで、自己肯定感が回復しやすくなります。
4. 職場の支援体制を活用する
園内での相談体制や研修制度を利用し、無理を一人で抱え込まないことが大切です。
5. プライベートを充実させる
仕事以外に「楽しい」と思える時間を確保することが心のバランスにつながります。散歩や音楽、カフェ時間など、ほんの短い時間でも構いません。
周囲の理解も大切
燃え尽き症候群は、本人だけでなく職場全体にも影響します。園としては、互いに声をかけ合い、相談しやすい雰囲気をつくることが重要です。管理職やリーダー層は、職員が安心して「疲れている」と言える文化を育てることが、燃え尽きの予防につながります。
燃え尽き症候群は「弱さ」ではなく、「それだけ一生懸命に向き合ってきた証」です。「もう十分に頑張っているな、私」「よくやってる!」「なんとかなるさ」など、心が上向きになるような‟自分への声掛け“言葉を作って、何かのときには心の中で唱えてみてください。
ストレスを発散したり、ときには愚痴を言い合ったり、自分の心身を守りながら、支え合える仲間と共に、長く安心して保育に携わることを大切にしていきましょう。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)