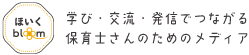保育士のメンタルに効くプチコラム「ぶるーむサプリ」です。
保育に役立つ心理学の新シーズン7回目は、「アンガーマネジメント」です。
あなたの職場はいかがでしょうか?
——————————————————–
生きていると、「怒り」という感情とどう向き合うか、
それがとても難しい場面に出会うことも多いですよね。
そんな怒りという感情とうまく付き合う方法として
「アンガーマネジメント」や「6秒ルール」という言葉を聴いたことがある人も多いかもしれません。
今日は「アンガーマネジメント」のお話です。
アンガーマネジメントとは、怒り(アンガー)を上手にコントロールし、適切に表現するための心理トレーニングや考え方です。1970年代にアメリカで生まれました。
ビジネスや教育、福祉の現場などで広く活用されています。
◆ アンガーマネジメントの基本的な考え方
1. 怒りは悪い感情ではない
怒りは、「自分にとって大切なものが脅かされた時」に自然に生じる感情です。
たとえば保育中に、「子どもが危険な目にあった」「園長や保護者から誤解された」などの理由で怒りを感じることもありますよね。
人間として当たり前、自分を危険なものから守ってくれる感情でもあります。
2. 怒りを「ぶつける」のではなく「扱う」
アンガーマネジメントは、その名の通り「怒り」という感情を「うまく扱う」こと。「怒らないようにする」のではなく、「怒っても適切に対応できるようになる」ことを目的としています。
◆怒りのタイプ
怒りのタイプとは、「どんなときに怒りやすいのか」「怒りをどのように表現しやすいのか」といった怒りの傾向やパターンを分類したものです。自分の怒りのタイプを知ることで、ついつい入ってしまう“怒りのスイッチ(きっかけ)”や思考の癖に気づきやすくなり、冷静な対応がしやすくなります。まずはそれに気づくことが、アンガーマネジメントの第一歩です。
代表的な怒りのタイプ5つをご紹介します。
① 正義感タイプ(正義型)
- 特徴:「こうあるべき」「ルールは守るべき」という考えが強く、秩序が乱れると怒りやすい。
- 口ぐせ:「普通は~するよね」「なんで守らないの?」
- 保育場面の例:時間通りに動かない保護者や、ルールに無頓着な職員にイライラ。
→◎対応:ルールを伝える際に“自分の価値観”として柔らかく伝える工夫を。
② 完璧主義タイプ(理想追求型)
- 特徴:物事をきちんとやりたい完璧志向。自分にも他人にも厳しい。
- 口ぐせ:「なんでできてないの?」「もっとちゃんとやって」
- 保育場面の例:掲示物のズレや片付けの甘さに強く反応してしまう。
→◎対応:80%でもできていればOK、と捉える“ゆるみ”を意識。
③ コントロールタイプ(支配型)
- 特徴:周囲を思い通りに動かしたい。期待通りに人が動かないとイライラ。
- 口ぐせ:「何度言ったらわかるの?」「こうしてって言ったよね」
- 保育場面の例:後輩保育士が自分の指示通りに動かず、怒りが湧く。
→◎対応:人にはそれぞれのやり方があると意識して、時には任せる練習を。
④ 自己防衛タイプ(不安型)
- 特徴:自信がなく、否定されたと感じると怒りに変わる。傷つきやすい。
- 口ぐせ:「どうせ私なんて」「また私が悪いって言いたいんでしょ」
- 保育場面の例:指摘されたことで、自分を否定されたと感じて怒る。
→◎対応:「これは攻撃ではなく、ただの情報である」と捉える練習を。
⑤ 我慢タイプ(抑圧型)
- 特徴:怒りを表に出さず、溜め込みがち。ある日突然爆発しやすい。
- 口ぐせ:「大丈夫です」「気にしてないです(でも本当は怒ってる)」
- 保育場面の例:日々の小さな不満が積み重なり、些細なことで大爆発。
→◎対応:不満をこまめに「伝える」「書き出す」習慣をつける。
◆ 実践に役立つ3つのテクニック
① 6秒ルール
怒りのピークは最初の6秒間。まず6秒間、深呼吸や数を数えて冷静になる時間を取ります。
② 怒りの温度計(10段階で表現)
自分の怒りを「今どれくらいか?」と数値化して、対応を決めます。
例:2/10ならスルー、8/10なら冷却時間が必要。
③ 自分の「べき思考」に気づく
「子どもは言うことを聞くべき」「同僚はもっと協力すべき」など、自分の価値観にこだわりすぎると怒りが増します。視野を広げて、柔軟に考える練習をすることが重要です。
アンガーマネジメントは、保育の質を高め、心地よい人間関係を築くための大切なスキルです。怒りを抑え込むのではなく、「うまく付き合う力」を育てることで、子どもにも大人にも安心できる関係性を築くことができます。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)