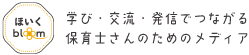保育に役立つ心理学の新シーズン8回目は、「自己有用感」です。
——————————————————–
子どもたちの成長を間近で支え、保護者や他の職員とも密に連携しながら、保育を進める大切な役割を担う保育士。
しかし日々の忙しさの中で、ふと立ち止まったとき「自分は本当に役に立っているのだろうか」「自分の保育は子どもたちの育ちにとって、良いものとなっているだろうか」と疑問に思うこともあるかもしれません。
今回は、保育士としての「自己有用感」(自分が周囲に対して価値を提供できているという実感)を高めるポイントをお伝えします。
――――――――
1.自己有用感とは何か
自己有用感とは、自分の存在や行動が周囲に貢献しているという感覚です。
心理学的には「自己効力感」とも関連し、自信やモチベーションを維持するうえで、重要な要素とされています。
自己有用感が高いと、仕事に対する意欲が湧き、ストレスへの耐性も高まることが知られています。
――――――――
2.保育現場での自己有用感が重要な理由
- 子どもとの信頼関係構築
子どもは保育士の小さな変化(表情や言葉のトーン等)にも敏感です。自己有用感を持って接することで、安心感や信頼感を子どもに伝えやすくなります。
例えば、もしあなたがが「自分がクラスの中で、役に立てている自信がない…」と思いながら保育をしているなら、その言動や表情から、子どもたちも「先生が不安そうにしている」ことを感じ取っているかもしれません。
「子どもがなかなかなつかない」「コミュニケーションしづらい子がいる」といったことで悩んでいるなら、あなた自身の自己有用感が低くなっている可能性があります。
- チームワークの向上
自分の役割に自信があると、同僚とのコミュニケーションも積極的になります。お互いを尊重し合う雰囲気が生まれ、園全体の士気向上につながるでしょう。できないことや苦手なことも賄い合い、チームとして一つになり、それがやがて、「私もここに居ていいんだ」「意見を言っても受容してもらえるんだ」という心理的安全性にもつながっていくでしょう。
- 持続的な成長と学び
自己有用感があれば、新しい保育スキルや教育プログラムにも前向きにチャレンジできます。結果として、自分自身のスキルアップにもつながります。
例えば、保育雑誌で見つけた面白い制作遊び。
「自分はまだ経験が浅いから、こんな提案をしても、受け入れてもらえないかな……」そんな場面でも、自信はなくても「こんなことやってみてもいいですか」と言える勇気を、“子どもたちも先生たちも喜んでくれる、私ならきっとできる”、そんな自己有用感が支えてくれるでしょう。
――――――――
3.自己有用感を高める3つのステップ
ステップ1:小さな「できた!」を記録する
毎日の保育で感じた小さな成功体験―「一緒に手をつないで歩けた」「初めて絵本を集中して聞いてくれた」など―をメモやスマホのアプリに記録しましょう。客観的なデータとして振り返ることで、「自分の働きは確かに成果をもたらしている」と実感できます。
ステップ2:フィードバックを積極的に受け取る
保護者からのお礼の言葉、子どもの笑顔、同僚や上司からの評価なども、自己有用感を支える重要な要素です。自分から「今日の保育でよかった点、改善点はありますか?」と声をかけ、他者の視点を取り入れましょう。
ステップ3:目標を具体的に設定する
「全員の名前を覚える」「季節の製作アイデアを3つ増やす」など、達成可能な短期目標を立てることで、日々の活動にメリハリが生まれます。目標を達成するたびに、自己有用感が積み重なっていきます。
――――――――
4.職場環境を活かす工夫
- 定期的なミーティングで共有する
成功事例や困りごとをチームで共有する場を設けると、職員同士が互いの貢献を認め合えます 。 - ロールモデルを探す
園内外の先輩保育士や講師の実践を観察し、成功のポイントを自分の保育に取り入れることで「自分もできる」という自信に繋がります。 - 休息とリフレッシュの時間を確保する
とはいえ自己有用感にばかり注目していたのでは、息がつまってしまいますよね。計画的に取得し、心身の余裕を保つことも、長期的な自己有用感の維持には欠かせません。
――――――――
自己有用感は、一朝一夕に手に入るものではありません。しかし、小さな成功体験の蓄積と周囲からのフィードバックを大切にし、具体的な目標を持って取り組むことで、着実に育んでいくことができます。
自己有用感が高まれば、保育士としてのやりがいが深まり、子どもたちの笑顔や成長を支える力も一層強くなるはずです。
人のためではなく、“自分らしく生きられている”そんな実感が、自己有用感。無理して自分をつくるということではありません。自分らしく輝くことで、自己有用感が高めていかれるといいですね。
———————————————————-
このコラムでは、皆さんからのお悩みを広く募集しています。
子どもたちのために働く、同じ仲間の立場から、
保育の仕事を楽しく続けるためのヒントについて、ご一緒に考えていきたいと思います♪
※医療的な内容については、専門家にご相談くださいね。
(文:鈴木聖子)